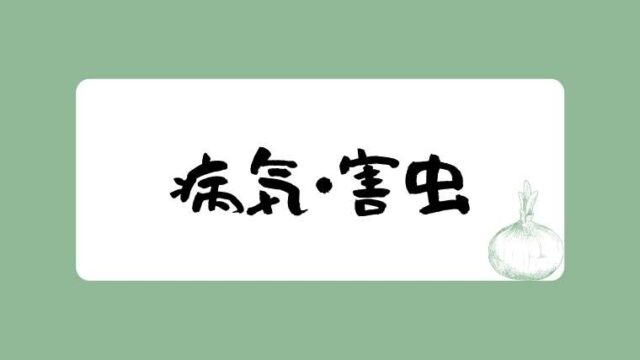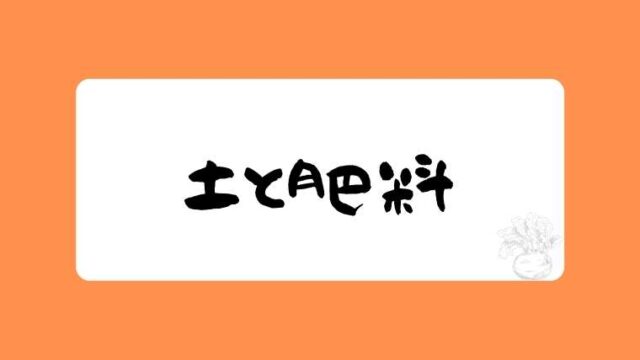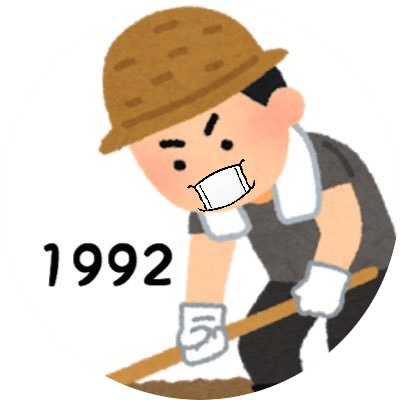1.枝豆栽培について

枝豆は、未熟な大豆の実で、原産はもちろん大豆と同じく中国・東南アジアです。
タンパク質、ビタミン、カルシウム、リン、鉄などを多く含み、栄養価に富んでいます。
2.枝豆の品種について

枝豆には400以上もの品種があると言われています。
色や味、香りへのこだわりから、福成(茶豆)、早生黒頭巾(黒豆)など、色々な品種が出てきました。
様々な品種を探してみるのも楽しみの一つです。
①湯上り娘(中早生、茶豆風味で食味が非常に良い)
②天ヵ峰(早生、実りが安定しており家庭菜園向き)
③白獅子(早生、草丈は低めで白花、白毛、77日で収穫可能)
④福獅子(中生、中間地では6月初旬までまける)
⑤夕涼み(中生、サヤが大きくて2〜3粒つく)
3.枝豆の育て方
土づくり

日当たりと水はけの良い場所を選び、半日日陰では収穫量が落ちます。
連作を嫌うので、前作がマメ科なら3〜4年は場所を替えて栽培しましょう。
まず、種まきの2週間前に苦土石灰を、1週間前に完熟堆肥、化成肥料をまき、土とよく混ざるように耕します。
次に、畝幅60cm、高さ10cmの畝を作りましょう。
適正の土壌酸度はpH6.0〜6.5です。
マメ科の野菜たちは空気中の窒素を固定して根に蓄えることができます。
根に感染する根粒菌を上手に着生させるため元肥は少なくしましょう。
種まき

発芽適温は15℃〜25℃、生育適温は20℃〜25℃ですが、低温、高温にも適応できるので、どこでも栽培できるのが特徴です。
遅霜の恐れがなくなる4月中旬以降から直まきができ、5月中に種まきを終えれば、害虫の被害を軽減できます。
地温が低いと発芽せず、まく時期が遅れると実が入りません。
中間地で4月〜5月いっぱいまでに種まきはおこないましょう。
直まき
直まきは1条まきで、株間20cmとしてまき穴1箇所に3〜4粒ずつまきましょう。
鳥害を防ぐには、発芽まで不織布などをかけて防除するか、ポットまきにします。
発芽しにくいので一晩水に浸けてからまくと良いでしょう。
ポットまき
ポットまきをするときは、7.5cm以上のポットに3〜4粒まき、土が乾いたら水を与えるようにします。
ただし、土を加湿状態にしてしまうと種が腐ったり、発芽不良の原因となるので注意してください。
発芽後、本葉が出てきた頃に2本に間引き、本葉が完全に展開したら畝へ植えつけます。
特に発芽直後の双葉は、よく鳥に狙われます。
そのままにしておくと食べられてしまうので、本葉が展開し始めるまでは寒冷紗をトンネルがけして保護しましょう。
カメムシがよく発生するのであれば、ミントと混植するのが良いでしょう。
ミントと混植することで、カメムシの飛来を抑えることができます。
管理
水やり

土が乾燥すると生育が遅れ、特に開花前に乾燥すると花が落ち、実が充実しないので、乾燥気味の際はしっかり水やりをしましょう。
開花期以降の乾燥もサヤの肥大不良の原因になります。
除草・土寄せ

株が成長して、草が目立ってきたら除草し、それと同時に株元に軽く土寄せを行います。
追肥

生育途中の追肥は特になくても構いません。
収穫

基本的に株ごと収穫しますが、株ごと収穫しない場合は、熟した下の方のサヤから収穫します。
枝豆の収穫適期は非常に短く、中の豆の形がはっきりとわかり、押したら飛び出そうなくらいサヤが膨らんだら適期です。
サヤが黄色くなると、枝豆本来の風味が失われてしまいます。
4.発生しやすい病害虫
斑点細菌病

小斑点を生じ、やがて拡大して中心部に穴があきます。
果実が直接地面につかないようにワラなどを敷いておくと良いです。
立ち枯れ病
地面に近い茎の部分が腐り、株が萎れて倒れます。
連作を避け、間引きを正しくおこない、風通しをよくしましょう。
深植えもよくないです。
アブラムシ
アブラムシは、新芽や葉裏に群生して、植物の汁を吸います。
筆などを使って払い落とすのが良いです。
カメムシ

カメムシは、葉や茎、サヤの汁を吸います。
見つけたら捕殺し、また薬剤散布をして駆除します。
シロイチモジマダラメイガ
淡緑色の幼虫がサヤの内部に侵入し、豆を食害しますので、サヤに侵入した穴を見つけたら、サヤごと処分しましょう。
マメヒメサヤムシガ
幼虫がサヤの表面を食害したり、葉をつづり合わせにします。
見つけたら捕殺し、つづり合わせた葉の中にも潜むので見つけて捕殺しましょう。
5.よくある生育不良
実がつかない
肥料が多いかカメムシの被害に遭っている可能性、または高温乾燥によるものがあります。
枝葉ばかりが茂るようなら、肥料の施しすぎか土に肥料分が残っていたと考えられます。
肥料が多いとは考え難く、葉が元気なのに実が落ちてしまうようなら、カメムシが原因です。
直ちに「スミチオン乳剤」などを散布して駆除しましょう。
また、枝豆の開花から肥大の時期に高温乾燥になるのも、実つきが悪くなる原因です。
開花している時期に、畑が極端に乾燥している時は水やりをしましょう。
株が倒れてしまった
株が小さいころは、倒れてしまうことがあります。
そのままにしておくとその後の生育に影響しますので早めに起こしてやりましょう。
真っ直ぐに立たせ、周囲の土を株元に寄せるようにし、土を押さえて安定させます。
葉が枯れる

立ち枯れ病か害虫の食害が原因です。
立ち枯れ病の場合は、地面に近い茎の部分が腐り、株が萎れて倒れます。
連作を避け、間引きを正しくおこない、風通しをよくしましょう。
害虫の食害の場合は、フキノメイガによる食害です。
早まきではあまり害虫の被害はありませんが、遅まきの場合は発生する場合があります。
よく見ると茎から虫糞が発生しており、茎を割ってみると、淡褐色の虫が内部を食い荒らしています。
葉裏に産みつけられる前に注意し、見つけ次第薬剤散布して防除しましょう。
6.まとめ
①マメ科の野菜なので連作は避ける。
②追肥は開花の頃から始める。また、この頃の乾燥に注意。
③防虫ネットなどでカメムシを防除する。
④種まき直後は鳥害にも注意する。
また、枝豆だけでなく枝豆を乾燥させてつくる「黒豆」も手間はかかりますが、楽しいです。
黒豆の中でも「丹波黒豆」は高級品で味も格別です。下記に黒豆の育て方を栽培記録を交えながら解説していますのでコチラも参考にしてください。
あと、枝豆の基本的な仕立て方も下記でまとめています。
下記では、100種類以上の野菜の育て方・栽培方法についてまとめています。